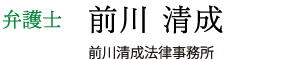成年後見制度
【高齢者の5人に1人】
厚生労働省によると、2025年には日本人の認知症患者が700万人に達します。700万人と言えば、65歳以上の日本人の5人に1人が認知症患者と言う計算です。日本は世界でトップクラスの長寿国になりましたが、その分、認知症も増えています。
【預金も引き出せない。施設と入所契約も結べない。】
もし認知症になってしまったら、本人はもちろん、配偶者も、子も、本人の銀行口座からお金を引き出すことはできなくなります。何故ならば、配偶者にとっても、子にとっても、本人の預金は法律上は「他人の預金」になるからです。 認知症になってしまったら、本人は「契約」もできません。したがって、介護施設に入所する契約も結ぶことができなくなります。
【成年後見人】
したがって、認知症になった場合、本人の代わりに財産管理や契約などをしてくれる人を選ぶ必要がありますが、民法は「事理弁識能力」を欠く「常況」にある者については、本人や家族からの請求があれば、家庭裁判所が「後見人」を選任すると定めています(民法第7条、第8条、第843条第1項)。 「事理弁識能力」と言うのは、ザックリ言って、善悪や損得を判断する能力です。「常況にある者」ですから、お酒を飲み過ぎて、一時的に意識を無くしたような場合は当たりません。 そして選任された後見人は本人のために、本人に必要な財産管理や契約などを行います(民法第859条第1項)。
【誰が後見人になる?】
最高裁の統計によると、後見人の8割は弁護士や司法書士などの専門職が選任されています。つまり本人にとっては「赤の他人」です。それでも構わないと思う方もいれば、もしも自分が認知症になった場合、配偶者や子に財産管理などを託したいと思う方もいらっしゃると思います。 自分が選んだ人に後見人になってもらいたい場合は、元気なうちに「任意後見契約」を結んでおく必要があります。
【任意後見契約】
任意後見契約と言うのは、元気なうちに、もしも認知症になった場合に備えて、自分で選んだ人(例えば配偶者や子)を後見人に指定し、「もしも」のときは選んだ人に介護や財産管理等を委ねる契約です(任意後見契約に関する法律第2条第1号)。但し、公正証書を作成する必要があります(任意後見契約に関する法律第3条)。 「もしも」になったら、本人や家族が家庭裁判所に「監督人」の選任を請求します(任意後見契約に関する法律第4条第1項)。後見人による介護や財産管理は、家庭裁判所が監督人を選任した時から始まります(任意後見契約に関する法律第2条第1号)。
認知症契約者の契約取消し
2024年8月27日の日経新聞朝刊に「認知症高齢者に不当契約」、「高齢の親、詐欺被害どう防ぐ」の見出しの下、悪徳不動産業者が認知症の80代女性をだまして、300万円で仕入れたアパートの1室を、10倍以上の3400万円で売りつけた事例が紹介されていました。日経新聞によると、多額の金融資産を所有する高齢者が増える一方で、認知能力の低下した高齢者が詐欺被害に遭う事件が増加しているようです。 そこで、今回は、悪徳業者にだまされて、お金を取られてしまった認知症高齢者がお金を取り返す方法についてご説明します。 なお、以下の記述では、その都度、悪徳業者や認知症高齢者と繰り返さずに、悪徳業者については「Y」、認知症高齢者については「X」と表記します。
【詐欺を理由に取り消す】
まず民法第96条第1項は「詐欺又は脅迫による意思表示は、取り消すことができる。」と定めています。したがって、XはYとの売買契約を詐欺を理由に取り消して、売買代金の返金を求めることが可能です。
【消費者契約法】
2001年に施行された消費者契約法は、次の通り詐欺を拡張して、消費者を保護しようとしています。 すなわち、契約に際して、(1)Yが重要事項について事実と異なったことを告げ、Xはそのウソを事実であると誤認した場合(「不実告知」と言います。消費者契約法第4条第1項第1号)、(2)Yが将来の価格など変動が不確実な事項について断定的な判断を示し(例えば「必ず値上がりします!」)、Xはその断定的な判断を確実だと誤認した場合(「断定的判断の提供」と言います。消費者契約法第4条第1項第2号)、(3)Yはわざと利益になる事項だけを説明して、不利益となる事項を説明しなかった場合(「不利益事実の不告知」と言います。消費者契約法第4条第2項)にもXはその契約を取り消すことができます。 さらに(4)Yが、Xは高齢や病気で判断能力が衰え、生活や健康に不安を抱いていることを知りながら、Xの不安をあおり、合理的な根拠がないのに、もし契約しなかったらXの生活が成り立たなくなるように言って勧誘した場合も、Xはその契約を取り消すことができます(消費者契約法第4条第3項第7号)。 要するに、何が詐欺が分かりにくいので、消費者契約法はいくつかのケースに関しては、詐欺か、否かにかかわらず、消費者に取消権を認めています。 なお、消費者契約法は「事業者」と「消費者」との契約について適用されますので(消費者契約法第2条第3項)、(1)、(2)、(3)、(4)、いずれのケースでもX(=認知症高齢者)に限らず、消費者(=事業者ではない個人。消費者契約法第2条第1項)と事業者間の契約であれば取り消すことができます。
【成年後見】
ところで、1で説明した詐欺であっても、2で説明した消費者契約法に基づく取消権であっても、多くの場合、悪徳業者はその事案が詐欺ではないとか、消費者契約法の定める要件を満たしていない等と争います。その結果、裁判で「白黒」をつけることになってしまいます。 ところが、認知症などによって「事理弁識能力」を欠く「常況」にある者については、本人や家族からの請求があれば、家庭裁判所は「後見人」を選任します(民法第7条、第8条、第843条第1項)。後見人は認知症高齢者の財産を管理するとともに(民法第859条第1項)、認知症高齢者の契約を取り消すこともできます(民法第9条)。詐欺であるか、消費者契約法の要件に該当するか否かを問いません。したがって、Xに後見人がいたなら容易にYとの契約を取り消すことができます。