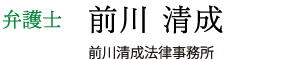共同親権
令和6年の通常国会で、民法のうち離婚や親権に関するルールが改正されました。施行時期はまだ決まっていませんが、来年5月24日までに施行されます。
こちらでは改正点のうち賛否が対立した「共同親権」についてご紹介します。
なお、以下では改正前の民法を「旧法」、改正後の民法を「新法」、改正されていない条文は、そのまま「民法」と表記します。
親権
旧法第818条第1項は「成年に達しない子は、父母の親権に服する。」と定めています。
成年に達する年齢は、明治以来、約140年間、20歳と定められていましたが、平成30年、18歳に引き下げられ(民法第4条)、令和4年から施行されています(改正附則第1条)。それでも、その後も多くの自治体では「成人式」を「二十歳の集い」と名前を変えて、18歳ではなく、20歳を迎える人たちを招いて開催されています。
それでは、「親権」とはどのような権利でしょうか。
民法に親権の定義はありませんが、戦後を代表する民法学者であった故我妻栄元東大教授は、親権に関して「親が子を哺育・監護・教育する職分である。」と述べています(親族法・有斐閣法律学全集316ページ)。
私も、権利というよりは、むしろ子どもを育てる義務と理解すべきだと思っています。民法第820条は「親権を行う者は、この利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」と定めており、今回の改正でも旧法第818条第1項は「親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。」と改正されたからです。
〔新旧対比〕
旧法第818条第1項 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
新法第818条第1項 親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。
親権の具体的な内容としては、子の居所の指定(民法第822条)、職業許可(民法第823条第1項)、財産管理(民法第824条)、身分行為の代理権(認知の訴えに関して民法第787条、氏の変更申立てに関して民法第791条第3項、養子縁組に関して民法第797条第1項、第815条、相続放棄に関して民法第917条)などがあります。
離婚後の親権
子の父母が結婚していたなら、父母が共同して親権を行います。旧法第818条第3項は「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。」、新法第818条第2項は「父母の婚姻中はその双方を親権者とする。」と定めています。
それでは、父母が離婚した後の親権はどのように行われるのでしょうか。離婚後の親権に関する819条は、次の通り改正されました。
〔新旧対比〕
旧法第819条第1項 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
第2項 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
新法第819条第1項 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。
第2項 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。
旧法、すなわち現行法においては、父母が結婚している間は共同して親権を行使しますが、父母の離婚後は、父か母、どちらか一方を親権者と定めなければならず、離婚後も父母がともに親権者となることを認めていませんでした。これを「単独親権制度」と言います。
これに対して、新法では、離婚後も父母双方が子どもの養育に責任を持つべきと立場から共同親権が導入されました。理想論はその通りです。しかし、父母(=夫婦)間の信頼関係が損なわれた故に離婚するに至ったのであり、諍いのある父母間で親権の行使に関して円満な協議を行うことは困難ではないか、という立場からの反対論も強く主張されました。一般論として、その通りだと、私も思います。
新法施行後、どのような場合に共同親権が合意されるのか、また家庭裁判所はどのようなケースにおいて共同親権と定めるのか、実務を見守る必要があろうかと思います。
令和6年、民法が改正されて、離婚後も「共同親権」が認められることになったと紹介しました(但し、施行時期は来春)。
しかし、一般的には、元々愛し合っていたはずの男女が、大げんかをして、その結果、離婚に至ります。大げんかした元夫婦が、協力して親権を行使することができるか、疑問はあります。それ故、離婚後、共同親権を認めていい場合もあれば、よくない場合も多いと思います。そこで、今回は、どのよう基準で親権者が決定されるのか、ご紹介します。
なお、以下では改正前の民法を「旧法」、改正後の民法を「新法」、改正されていない条文は、そのまま「民法」と表記します。
親権者をどちらにするか、父母の協議がまとまらない場合、家庭裁判所が親権者を定めます(民法第819条第5項)。
その時の判断基準は「子の利益のため」です(新法第818条第7項)。
家庭裁判所は「子の利益のため」の視点で、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければなりません。母が子を虐待する場合や、DVのように父母が共同して親権を行うことが困難な場合は単独親権を決定します(新法第818条第7項)。
法律上、子どもの意思は考慮要素に掲げられていません。何故なら親権者の決定は裁判官が自らの責任で行うべきであり、子どもに責任転嫁することは許されないからです。
もっとも、家庭裁判所の審判においては、子どもが意見を述べたり、家庭裁判所調査官が子どもの希望を聴取するなどして、子どもの意思も考慮されます(家事事件手続法第65条)。
財産分与
こちらでは、令和6年に改正された民法のうち「財産分与」に関する改正点をご紹介します。
なお、今回も改正前の民法を「旧法」、改正後の民法を「新法」と表記します。
離婚に伴う「お金」
財産分与の改正点をご説明する前提知識として、夫婦が離婚したときに動く4種類のお金についてご説明します。
①〔慰謝料〕
1つは、結婚関係を破綻させた者(ザックリ言うと「悪い方」。例えば不貞行為を行った者)が支払う「慰謝料」です。
もっとも、日本の裁判所では高額な慰謝料を認めることはありません。ボリュームゾーンは200万円から300万円です。
②〔養育費〕
次に「養育費」です。例えば、離婚後、母が未成熟の子を引き取り、育てる場合、父が母に対して支払います。
養育費の額は、未成熟の子が負担義務者(上記の例では父)と同程度の生活水準を維持することができる金額です。最高裁は、養育費の相場に関して、父母の収入に応じた「速算表」を公表しています。
③〔財産分与〕
3つ目が、結婚期間中に蓄えた夫婦の財産の清算です。これを「財産分与」と言います。
財産分与の対象となるのは、結婚、同居期間中に蓄えた財産です。将来支給されるであろう退職金も財産分与の対象になります。
これに対して、結婚前から持っている財産や、相続で得た財産など夫婦の協力とは無関係に取得したものは「固有財産」と言って、財産分与の対象とはなりません。別居期間中に蓄えた財産も対象にはなりません。
④〔年金分割〕
離婚した夫婦間で直接お金が動く訳ではありませんが、「年金分割」という仕組みが創設され、平成19年から施行されています。ザックリ言うと、結婚期間中の年金の「2階建て部分」(サラリーマンであれば厚生年金)の保険料納付記録を原則2分の1ずつに分割する制度です。例えば、会社員や公務員の夫と、専業主婦の妻が離婚したケースでは、従来、妻には十分な年金が支給されませんでした。そこで、年金分割は、結婚期間中に夫が支払った厚生年金保険料に関して、その半分は妻が支払ったことにします。この結果、妻にも厚生年金が支給されることになります(その分、夫の年金は減ります)。
財産分与を請求することができる期間-2年から5年へ
以上を前提に、財産分与の改正点をご説明します。
旧法は、財産分与を請求することができる期間を、離婚から2年以内としていましたが(旧法第768条第2項但書)、新法はこの期間を5年に延長しました。但し、新法の施行日よりも前に離婚した場合は2年です(改正附則4条)。
財産分与の基準-原則折半
財産分与の清算割合は、財産形成や維持に関する各自の寄与度によって決まります。かつては専業主婦に関して、その寄与度は3、4割程度に評価されることが多かったのですが、次第に家事労働を高く評価するようになり、現在の実務では清算割合を原則として2分の1とする運用が定着していました。新法は「婚姻期間中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかではないときは、相等しいものとする。」と書き加えて、この実務の運用を明文化しました(新法第768条第3項)。
この点、とりわけ年配の男性からの不満をしばしば耳にします。「オレが働いて、稼いだカネなのに」と。
確かに、「昭和」の日本では、夫が外で稼いで、妻が家事や子育てを担当する結果、夫名義の財産が多く、妻名義の財産は少ない場合が多いと思いますが、家事労働に対する評価が高くなったこと、上記の通りです。また財産分与とは「生き別れ」時の清算です。「死に別れ」時の清算(=相続)において配偶者の法定相続分は2分の1ですから(子と配偶者が相続人の場合。民法第900条第1号)、「生き別れ」の場合も2分の1ずつが自然だろうと思います。