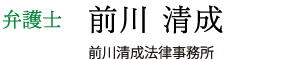多重債務の救済方法
病気や失業、事業の失敗、保証人になってしまったなど様々な理由で、サラ金やカードから多額の借金をしてしまい、生活が困窮した場合(「多重債務」と呼ばれています)、かつては①自己破産か、②民事調停、③任意整理しか救済メニューがありませんでした。そのうち、民事調停や任意整理は全ての債権者から同意を得る必要がありますが、サラ金やカード会社は、分割払いの場合、元金のカットに応じませんし、短期間の完済を求めます。その結果、多重債務からの救済手段としては自己破産が主要な役割を担っていました。
自己破産の限界
(1) ギャンブルや浪費による借金
ただ、自己破産しても、多重債務に至った原因がギャンブルや浪費などの場合、免責(=借金の免除)が得られません(破産法第252条第2項)。確かに、たとえ高利貸しといえども大事なお金を貸しているので、裁判所がパチンコやキャバクラで作った借金を免除にしてしまうことは、我々の法感情と相容れないのかも知れません。とはいえ、医者が酒を飲み過ぎて病気になった患者に対して「自業自得です。死ぬしかありません」と言わないように、弁護士もパチンコやキャバクラが原因で首が回らなくなった多重債務者に対して「夜逃げするしかありませんね」とは言えません。ギャンブルや浪費などが原因で多重債務に陥った人たちに対しても救済メニューが必要なはずです。
(2) マイホームを失いたくない
破産は債務者の財産を清算する手続きです(但し、めぼしい財産がなければ清算手続きは省略されます。これを「同時廃止」と言います)。したがって、自宅も手放すことになりますが、生活の本拠である自宅を失うと多重債務からの更生が困難になることが少なくありません。
個人再生手続の創設
そこで、2000年、民事再生法が改正され、5年以内に法律が定める「最低弁済額」を支払ったなら、残りの借金は免除される個人版の民事再生手続き(小規模個人再生と給与所得者等再生)が創設されました。
小規模個人再生
紙幅の都合がありますので、以下では申立件数の約95パーセントを占める「小規模個人再生」についてご説明します。小規模個人再生は個人事業者に限らず、給与所得者も利用可能です。
(1) 利用できるのは?
小規模個人再生を利用できるのは、ⓐ住宅ローンや抵当権でカバーされていない債務、言い換えると無担保の借金の合計が5000万円以下で、ⓑ将来において継続的または反復的に収入を得る見込みのある、ⓒ個人です(民事再生法第221条第1項)。
(2) 最低弁済額
最低弁済額は下記①及び②を超える額です。
①基準債権額の5分の1(但し、基準債権額が3000万円以下の場合。基準債権額が3000万円を超える場合は10分の1。民事再生法第231条第2項第3号、第4号)。基準債権額とは、ザックリ言うと住宅ローン以外の借金です。
但し、最低弁済額は、基準債権額が100万円未満なら、全額。基準債権額の5分の1が100万円未満なら、100万円。基準債権額の5分の1が300万円以上なら、300万円です。表にすると、次の通りです。
②破産の場合の配当額よりも多い額(清算価値保障原則。民事再生法第230条第2項、第174条第2項第4号)
(3) ギャンブルや浪費による借金も免責
民事再生法には、破産法とは異なり、「ギャンブルや浪費による借金は免除しないぞ」と定めた条項がありません。したがって、ギャンブルや浪費が原因で多重債務に陥ったとしても、最低弁済額を返済すれば、残りの借金は免除されます。
(4) マイホームの確保
住宅ローンを契約通り支払い続け、自宅を維持したい債務者については、「住宅資金特別条項」を定めることで自宅に住み続けることが可能になりました。住宅ローンに関しては、(2)でご説明した最低弁済額とは別枠で返済を続けます。
因みに、個人再生手続の立法作業においては、私の司法試験受験研究室の先輩で、当時、法務省民事局へ出向していたS裁判官が中心的な役割を果たしました。私はS先輩の活躍や、ギャンブルや浪費が原因の借金からも法的救済を図り、自宅や自動車を手放すことなく経済的更生を可能にする仕組みなどドラスティックな改革を目の当たりにして、「法律が変われば、社会がよくなる」と確信し、2004年、参議院選挙に挑戦することを決意しました。